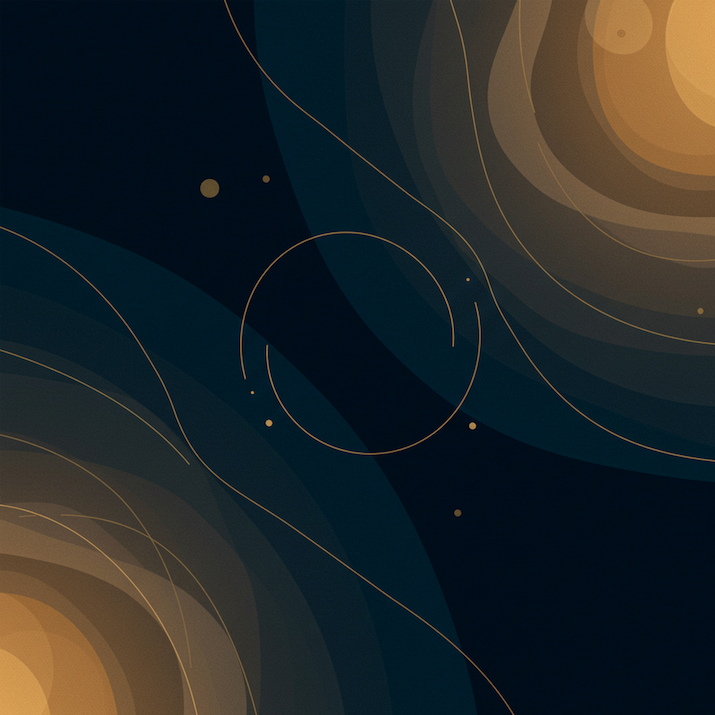はじめに
この記事は、『BEING ON EARTH』の第8章:内側からの現れ(ロナルド・ブレイディ)の内容を要約しながらご紹介するものです.作成にあたってはAIを活用しています.誤りがないとも言えませんので、その点ご了承ください.
原文はこちらで確認できます(英語pdf)
この論文は、美と理解可能性の深い関係を探求し、私たちが世界を知覚し認識する過程の根本的な性質を問う、極めて哲学的で実践的な考察です。著者ロナルド・ブレイディは、芸術体験と日常的知覚の分析を通して、「知覚は内側から始まる」という革新的な認識論を提示しています。
論文全体の出発点となるのは、ブレイディの恩師アシェンブレナー教授が残した印象深い言葉です。「そう、何となく美しい対象ほど、いつもより理解しやすいものなのです」。この一見逆説的にも聞こえる洞察が、論文の探求すべき主題を定めています。興味深いことに、アシェンブレナー教授はカント哲学の専門家でありながら、このような「非カント的な見解」を抱いていました。後にブレイディが発見するように、教授の洞察はバウムガルテンの美学やトマス・アクィナスの「明晰性」概念といった思想的伝統に根ざしていた可能性があります。
論文は四つの主要な部分から構成されています。まず、知覚における「内側からの理解」を牛の写真の例で説明し、次に建築体験における身体的理解を論じます。続いて、ブランクーシの彫刻作品を詳細に分析し、芸術が如何に「身振り」を通して本質を伝えるかを示します。最後に、これらの考察を「現象の進化」という壮大な展望に結びつけ、認識力の発展を個人的課題から共同体的課題へと拡張する必要性を論じています。
この論文が提起する根本的な問いは、私たちがより豊かで完全な知覚の世界を築いていく責任を、個人としてだけでなく社会として受け入れるかどうかということです。芸術教育と自然観察の技能を統合し、「現象の進化を助ける」共同の取り組みが、人間の認識能力の発展にとって不可欠だという主張は、現代の教育や文化政策にとっても重要な示唆を与えています。
美と理解可能性の関係について
この章は、著者ロナルド・ブレイディがバークレー大学でイマヌエル・カント1哲学を学んでいた時の体験から始まります。カール・アシェンブレナー2教授という恩師との印象深いやりとりが紹介されています。
ブレイディは学生時代、カントの哲学を批判的に検討することに熱心でしたが、アシェンブレナー教授は批判よりもまずカントを理解することを重視していました。教授は学生の批判的な姿勢に忍耐強く付き合い、読みにくい論文にも時間をかけて向き合ってくれる優しい人でした。
ブレイディがバークレーを離れる際、ゲーテと美的体験と知識の関係について研究していることを話すと、教授は静かにこう言いました。「そう、何となく美しい対象ほど、いつもより理解しやすいものなのです」。この言葉は、後の研究における重要な指針となりました。
興味深いことに、後年ブレイディが図書館でアレクサンダー・ゴットリープ・バウムガルテン3の翻訳を探していた際、偶然にもその翻訳者がアシェンブレナー教授だったことを発見します。教授は自分が翻訳者であることを一言も言わなかったのです。美と理解可能性を結びつける教授の洞察は、バウムガルテンの美学や、トマス・アクィナス4の「明晰性」の概念から来ていた可能性があります。
知覚における「内側からの理解」
ブレイディは、美からではなく「理解可能性」から議論を始めることを提案します。ここで「牛の写真」という具体例が登場します。
この写真を最初に見ると、左上から飛び掛かる猫や、右側の小鳥(あるいはネズミ)といった複数の解釈が可能です。しかし、これらの解釈では写真全体が統一された意味を持ちません。猫が獲物に向かっているとしても、その動きに説得力がなく、場面全体が一貫していないのです。
ところが、写真を時計回りに90度回転させると、突然すべてが変わります。左側に牛の頭が現れ、黒い耳、目、鼻面が見えてきます。まるで鍵でドアが開かれたように、白い牛の全体像が浮かび上がります。牛は写真全体を占め、太陽が右から照らし、左の針金の柵も自然に場面に溶け込みます。私たちは頭を向けて注意を向けてくる動物と向き合うことになるのです。
ここでブレイディが指摘する重要な点は、牛が私たちに注意を向けることで感じる感覚と、私たち自身が牛に注意を向ける意識とが切り離せないということです。私たちの内側にある何かが、外側から出会ってくるもののの内側を明らかにするのです。
この観察から、ブレイディは「知覚は内側から始まる」という大胆な仮説を提示します。知覚対象の「内側」が明らかになるのは、私たち自身の内側においてなのです。
歴史的建築様式の体感的理解
次にブレイディは、ロマネスク様式5とゴシック様式6の建築を例に挙げて、私たちがどのように建築空間を体験するかを説明します。
ロマネスク様式の特徴である完全な円形アーチの下に立つと、地面深くのトンネルの中にいるような感覚を覚えます。一方、ゴシック様式の尖頭アーチを持つ大聖堂の身廊に立つと、上に引き上げられるような感覚が生まれます。
これらの建築様式は、隣接する石材同士の圧力に依存した構造原理を持っています。円形アーチは四方からの圧力によってより安定になりますが、ゴシックアーチは高い位置で荷重を相互に支え合う支持柱の原理で成り立っています。
ブレイディは読者に実験を提案します。同じくらいの大きさの人と一緒に、重い石を二人の頭上できるだけ高く持ち上げ、注意深く少しずつ離れていく動作をしてみるのです。この時、それぞれの人がゴシックアーチの片側の機能を表現し、重い石を支えるために維持しなければならない繊細な力のバランスを体感できます。
私たちがこれらの建築形式の構造工学的原理を理解すると、自分の体がその力学的状況に関与していることを想像せずにはいられません。私たちの手足と関連する内的な感覚器官が、建物の内的一貫性への理解を開くのです。まるで鍵がドアを開けて、以前は遠くから眺めるだけだった構造により親密に関わることができるようになるかのようです。
ブランクーシの彫刻における「見る技術」
造形芸術の作品を見ることには、特別な技能と知識が必要です。詩を読むのに特別な言葉の使い方を理解する必要があるように、造形芸術を「見る」ことには、その作品が要求する「見る人の語法」を習得することが必要なのです。
美術館で特定の作品を価値がないと判断する時、それは趣味の違いではなく、必要な知覚の様式を習得できていないことが原因かもしれません。その場合、実際の作品ではなく、別の何かを判断していることになります。
この問題は、ルーマニアの彫刻家コンスタンティン・ブランクーシ7とアメリカ税関の間で起こった有名な裁判事件8(1926-28年)によく表れています。ブランクーシが『黄金の鳥』をニューヨークに持ち込んだ際、税関はこれを芸術作品として認めず、金属としての価値に対して210ドルの関税を課しました。裁判では、税関側の証人たちが「これは鳥ではない」と証言し、いかなる変化を加えても鳥には見えないと主張しました。
『新生児』の段階的発展
ブランクーシの『新生児』という作品を通して、芸術家がどのように表現を洗練させていったかを見ることができます。
まず『第一歩』という作品では、幼児の顔の特徴が目-眉-鼻の複合体と口に簡略化されて表現されています。この頭部は最初の一歩を踏み出す子供の体の上に載っていて、全体の文脈は明確でした。
次の『第一声』では、目、眉、鼻の曲線が保たれ、耳も見えるようになっています。これは誕生時の覚醒の瞬間、医師が新生児の背中を叩いて肺を使わせる時の叫びを表現しようとしたものです。
最終的な『新生児』では、タイトルから「叫び」への言及が削除されています。目-鼻の曲線が平坦な面まで延び、これが幼児の大きく開いた口を表現し、顎によって区切られています。この作品を幼児の頭として見るなら、それは明らかに泣いている、いや号泣している幼児です。
この発展過程で重要なのは、ブランクーシが顔の幾何学的形状ではなく、泣いている幼児の身振り9を捉えようとしていることです。最終的な像は、実際の子供よりも内的意味により透明で、より深く理解できるものになっています。
身振りの認識と芸術の透明性
身振りを認識する能力は、私たちが共有する基本的な知覚能力です。これは私たちが世界を理解するための不可欠な基礎であり、人間関係、動物との関わり、さらには植物との関わりにおいても取って代わることのできないものです。
ブランクーシは世界で目撃した身振りの力に深く影響を受け、それらを提示する彫刻形式を発展させました。例えば、オーギュスト・ロダン10のアトリエで制作された『苦悶』という作品は、弟子が師匠に殴られているのを目撃した時に構想され、無力な諦めの身振りが像に形を与えました。
興味深いのは、ブランクーシが自分の作品の写真撮影にも独特のアプローチを開発していたことです。美術館の標準的な写真と比べて、ブランクーシ自身が撮影した写真は、ソフトフォーカス、撮影角度、照明によって作品をより内的意味に透明なものにしています。身振りと形がより明確になり、作品の本質がより深く見えるため、作品がより「生きて」見えるのです。
『マイエストラ』における動きの表現
マイエストラ11(ルーマニア民話の魔法の鳥の名前)という作品は、物理的詳細の類似を求める人には奇妙に見えるかもしれません。しかし、鳥の動きや身振りの文脈を考慮すると、全体の印象が変わります。胸と肩の筋肉、持ち上がる頭は、私たちが日常的に見る鳥の世界を思い起こさせます。
写真家エドワード・スタイケン12がこの作品を庭の石柱に設置した時、彼の娘が太陽光の当たった像を撮影した写真は驚くべき結果を示しました。後ろから適切な光が当たると、大きな猛禽の瞑想的な身振りを見逃すことが不可能になるのです。
この作品の極端な透明性は、不必要な要素を削減することで実現されています。これにより、内的同一性への直観が外的要素を単一の身振りに統一することが可能になり、内と外が密接に近づく世界が創造されます。重要なのは、内的性質が外的形状を通して明らかになることです。前者が後者の組織化をもたらすからです。
現象の進化と認識の発展
日常知覚の限界
芸術作品において内と外が近づくことについて語れるのは、日常的知覚が「明確な内側のない外側の世界」を提示するという性格を持っているからです。世界が謎めいて見えるのは、まさにこの経験の性格のためなのです。
知覚は命題的な「について」の知識ではなく、知覚対象の直接的把握である「の」即座の知識です。しかし、この知識は明らかに不完全です。理解可能な世界を認識するために私たちが持ち出す意図は、全体的な課題には不適切であり、二つの面で不足しています。多くのものを未知のままにし、科学的探究によってのみ到達可能にしていること、そして、あまりにも多くのものを見えないままにしていることです。
ブランクーシの方法が特別なのは、自然において彼の彫刻のように明瞭で統一された像を見つけることが稀だからです。どんな現実においても、物事の単純な性質以上のものが表現されており、世界の他の部分がそれに影響を与えています。ブランクーシは、意図された身振りではないすべてのものを洗練して取り除くか、表現する気分に完全に身を委ねた身振りを示す主題を選ぶことで、この問題を解決しました。
認識力の個人的発展と社会的意義
現在、認識力の涵養は各個人の文化的課題として受け入れられていますが、科学的知識の涵養とは異なり、主として個人的課題のままです。これは、私たちの社会が知覚像を成人にとって完全なものと見なしてきたことの証拠ですが、実際には平均的な知覚像はかなり可塑的で、相当な発展が可能なのです。
野外植物学者、猟場番、薬草採集者、野外地質学者などの専門技能は、私たちの文化的展望にとって遠く神秘的な達成として見られがちです。一方で、芸術作品を見たり聞いたりすることに関わる技能は広く認識されています。しかし残念ながら、これらの技能は芸術的産物にのみ関わると考えられており、自然現象には必要ないとされています。
実際には、これらの追求はすべて認識力を拡張し、知覚像をより完全にします。例えば、野外で植物の同定を行う植物学者は、種を容易に認識できるようになります。なぜなら、以前は匿名の雑草だったものを、組織化する直観に対してより透明にすることができるようになったからです。
認識の瞬間において、知覚することと知ることは同一です。見る者のみが知ることができ、知る者のみが見ることができるのです。このような技能が発達した個人的なものから生じるとしても、それが個人的なままでなければならないということにはなりません。
共同の課題としての「現象の進化」
ブレイディが最終的に提起する重要な問題は、「現象の進化を助ける」ことを個人の課題としてではなく、共同体の課題として受け入れるかどうかということです。新しい見る様式は存在の新しい啓示を伴い、科学における新しい理論的命題と同様の重要性を持っています。
私たちは道の曲がり角ごとに、感受性のある目に不完全な性格を明らかにし、成長の可能性を示す像を見ています。見ることと知ることの統一は長い間芸術的表現の中心でしたし、専門家たちは他の人々を自分たちのようになるよう訓練することができました。
この問題への答えは、やや遠い未来にしか到着しないでしょう。しかし、この問題は今日、私たちと共にあるのです。私たちは個人として、そして社会として、より豊かで完全な知覚の世界を築いていく責任を持っているのではないでしょうか。
脚注
1 イマヌエル・カント(Immanuel Kant, 1724-1804) – ドイツの哲学者です。『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』の三批判書で知られます。特に『判断力批判』では美的判断の性質を詳細に分析し、美と崇高の概念を体系化しました。本論文でアシェンブレナー教授が「美しい対象ほど理解しやすい」と述べたのは、カントの美学とは対照的な立場を示しています。カントは美的判断を利害関心のない純粋な判断として捉えましたが、ブレイディが論じる美と理解可能性の統一は、より直接的で体験的な認識論を提示しています。 ↑
2 カール・アシェンブレナー(Karl Aschenbrenner, 1913-1997) – カリフォルニア大学バークレー校の哲学教授で美学研究者でした。本論文では、ブレイディの恩師として登場し、「美しい対象ほど理解しやすい」という重要な洞察を与えた人物として描かれています。後にブレイディがバウムガルテンの翻訳を探していた際、偶然にもアシェンブレナーがその翻訳者だったことが判明します。この事実は、美と理解可能性を結びつける教授の洞察の哲学的背景を示唆する重要なエピソードとなっています。 ↑
3 アレクサンダー・ゴットリープ・バウムガルテン(Alexander Gottlieb Baumgarten, 1714-1762) – ドイツの哲学者で、「美学(Aesthetica)」という用語を初めて学問分野として確立した人物です。1750年の主著『美学』において、感性的認識の完全性としての美を論じました。アシェンブレナー教授がバウムガルテンの翻訳者だったという事実は、美と理解可能性を結びつける教授の洞察の源泉を示唆しています。バウムガルテンの美学は、理性的認識と感性的認識を統合しようとする試みであり、ブレイディの論文における「内側からの知覚」という概念の哲学的背景となっています。 ↑
4 トマス・アクィナス(Thomas Aquinas, 1225-1274) – 中世スコラ哲学の代表的神学者・哲学者です。美の本質を「完全性(perfectio)」「釣り合い(proportio)」「明晰性(claritas)」の三要素で説明しました。特に「クラリタス」は、対象の本質が明確に現れ出る性質を意味し、本論文でアシェンブレナー教授の「美しい対象ほど理解しやすい」という洞察の可能な源泉として言及されています。この概念は、ブレイディが論じる芸術作品の「透明性」—内的意味が外的形式を通して直接的に伝わる性質—と密接に関連しています。 ↑
5 ロマネスク様式 – 10-12世紀ヨーロッパの建築様式です。厚い石壁、小さな窓、半円アーチ、筒形ヴォールトが特徴です。本論文では、この様式の空間体験が「地面深くのトンネル」のような感覚をもたらすと分析されています。ブレイディは、私たちがロマネスク建築の構造原理—四方からの圧力による安定性—を理解する時、自分の身体がその力学的状況に関与していることを想像すると論じています。これは「内側からの知覚」という論文の中心概念を建築体験を通して説明する重要な例となっています。 ↑
6 ゴシック様式 – 12-16世紀の建築様式です。尖頭アーチ、リブ・ヴォールト、飛び梁、大きなステンドグラス窓が特徴です。本論文では、ゴシック大聖堂の身廊で感じる「上に引き上げられる感覚」が分析されています。ブレイディは読者に実験を提案し、二人で重い石を頭上に持ち上げて徐々に離れる動作により、ゴシックアーチの力学的原理—高い位置での相互支持—を体感できると説明しています。この体験的理解は、建築の構造工学的原理と身体感覚の統一を示しています。 ↑
7 コンスタンティン・ブランクーシ(Constantin Brâncuși, 1876-1957) – ルーマニア出身の彫刻家で、20世紀抽象彫刻の先駆者です。パリで活動し、対象の本質的な形を追求する独特の様式を確立しました。本論文では彼の『新生児』『第一歩』『第一声』『マイエストラ』『黄金の鳥』などが詳細に分析されています。ブレイディは、ブランクーシの作品が物理的類似ではなく「身振り」や「内的本質」を捉えることで、見る者に深い認識をもたらすと論じています。1926-28年のアメリカ税関との裁判は、抽象芸術の社会的認知を巡る重要な事件となりました。作品画像は以下で確認できます:https://www.moma.org/collection/works/81033 (Bird in Space), https://www.philamuseum.org/collections/permanent/51359.html (The Newborn) ↑
8 1926-28年 ブランクーシ対アメリカ税関裁判 – 抽象芸術が法的に「芸術」として認められるかが争われた画期的な裁判です。ブランクーシが『黄金の鳥』をニューヨークに持ち込んだ際、税関が芸術品として認めず金属としての価値に課税した事件です。本論文では、この裁判が「見る技術」の重要性を示す事例として言及されています。税関側証人たちの「これは鳥ではない」という証言は、適切な「見る人の語法」を習得していない観察者の限界を表しています。この事件は、芸術の社会的認知と教育の重要性を浮き彫りにしました。最終的にブランクーシが勝訴し、抽象芸術の芸術的地位が法的に認められることになりました。 ↑
9 身振り(gesture) – 本論文において単なる物理的動作ではなく、内的本質が外的形式に現れる表現として定義されています。ブレイディは、身振りの認識が人間の基本的知覚能力であり、人間関係や動物との関わりにおいて不可欠だと論じています。ブランクーシの彫刻は、対象の身振りを純化・抽出することで、見る者により深い認識をもたらします。『新生児』における「泣く幼児の身振り」や『マイエストラ』における「猛禽の身振り」の分析は、芸術が如何に身振りを通して本質を伝えるかを示しています。これは単なる形の模倣ではなく、動きや意図の本質的な表現なのです。 ↑
10 オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin, 1840-1917) – フランスの彫刻家で「近代彫刻の父」と称されます。『考える人』『地獄の門』などの代表作で知られます。ブランクーシは若い頃ロダンのアトリエで学びましたが、後に師の様式から離れて独自の道を歩みました。本論文で言及される『苦悶』は、ブランクーシがロダンのアトリエで弟子が師匠に殴られる場面を目撃して制作した作品で、「無力な諦めの身振り」を表現しています。この作品は、ブランクーシが現実の身振りから芸術的形式を抽出する手法を示す初期の重要な例として論じられています。 ↑
11 マイエストラ – ルーマニア民話に登場する魔法の鳥です。ブランクーシの故郷の文化的背景を反映した作品名で、作家の民族的アイデンティティと芸術的表現の関係を示しています。本論文では、この作品が物理的詳細の類似ではなく「鳥の動き」「身振りの文脈」を表現していると分析されています。スタイケンの庭での設置と偶然の写真撮影により、作品の真の「猛禽の身振り」が明らかになった事例は、適切な文脈と条件下でのみ芸術作品の本質が現れることを示しています。この作品は、抽象化によって本質をより明確に表現するブランクーシの手法の典型例です。 ↑
12 エドワード・スタイケン(Edward Steichen, 1879-1973) – アメリカの写真家で、ファッション写真、戦争写真、植物写真の分野で革新的な作品を残しました。ニューヨーク近代美術館(MoMA)の写真部門設立にも関わりました。本論文では、スタイケンがブランクーシの『マイエストラ』を自宅の庭に設置し、彼の娘が偶然撮影した写真が紹介されています。その写真は、適切な光の条件下で彫刻が「大きな猛禽の瞑想的身振り」として現れることを示し、ブランクーシ作品の「透明性」を証明する重要な事例として分析されています。この出来事は、芸術作品の本質が適切な環境と視点によって初めて現れることを物語っています。 ↑