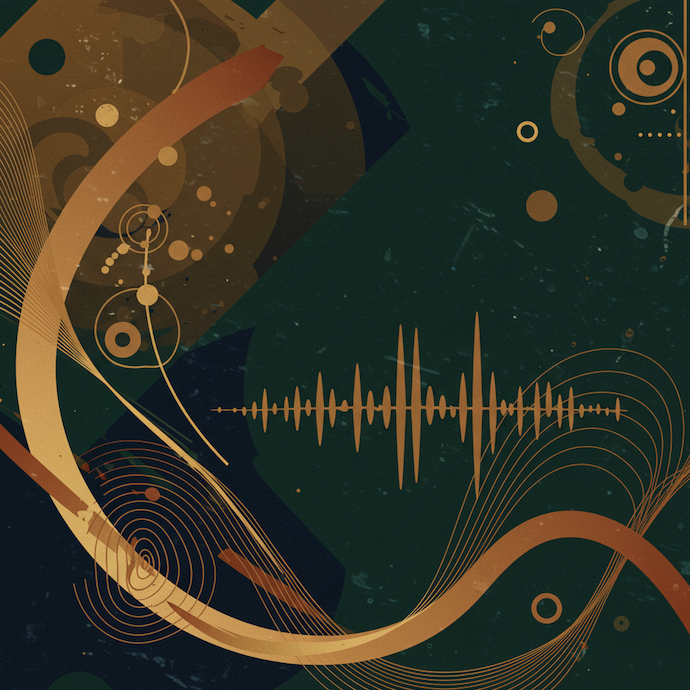はじめに
この記事は、『BEING ON EARTH』の第7章:春の祭典(スティーヴン・エーデルグラス)の内容を要約しながらご紹介するものです.作成にあたってはAIを活用しています.誤りがないとも言えませんので、その点ご了承ください.
原文はこちらで確認できます(英語pdf)
この章では、ストラヴィンスキーの「春の祭典」という具体的な楽曲の分析を通じて、20世紀音楽が持つ革新性と、音楽の受容が時代とともに変化する様子を探求しています。
著者は巧妙な論理構成を取っています。まず「春の祭典」の冒頭部分を詳細に分析し、従来の音楽とは根本的に異なる特徴(変化し続ける拍子、不協和音、多調性など)を具体的に示します。次に、これらの特徴が20世紀音楽全体に共通する革新的要素であることを明らかにし、そうした音楽を理解するには聴き手側の新しい姿勢が必要だと論じます。
そして最後に、1913年の初演時には「暴動」を引き起こすほど受け入れ難かった音楽が、現代では自然に理解され楽しまれているという歴史的変化を示すことで、芸術作品の意味は時代とともに変容するものであることを示唆しています。一つの楽曲から出発して、音楽史全体、さらには芸術受容論にまで視野を広げる、非常に密度の高い論考となっています。
冒頭の印象的な音楽
ストラヴィンスキーの「春の祭典」1は、ファゴット2という楽器の独奏で始まります。このファゴットは普通よりもずっと高い音域で演奏されるため、とても独特で幻想的な響きを生み出します。まるで宙に浮かんでいるような、現実から切り離されたような不思議な音色です。
この冒頭の旋律は軽やかに揺れるような特徴を持っていますが、聞く人の体を自然にリズムに合わせて動かしたくなるような魅力があります。しかし同時に、この音楽は私たちに注意深く耳を澄ませることを求めます。なぜなら、拍子3が小節ごとに絶えず変化しているからです。
普通の音楽では、4拍子や3拍子といった一定のリズムパターンが続くため、私たちは無意識に足でリズムを刻むことができます。しかし「春の祭典」では、4拍の次に3拍、また4拍、そして2拍というように、拍子が次々と変わっていきます。つまり旋律は、常に変化し続ける時間的な枠組みの中で流れているのです。
音楽の重なりと複雑さ
最初のファゴット独奏に、今度は普通の音域で演奏される第2ファゴットが加わります。この第2ファゴットは最初のファゴットよりも暗く、地に足のついた音色を持っています。2つの旋律線を同時に追うことはそれほど難しくありませんが、これらの和音は不協和音4、つまり古典的な音楽理論で期待される美しい響きとは異なるものです。
従来の音楽では長調や短調といった決まった調性の枠内で作曲されることが多いのですが、ストラヴィンスキーはそうした制約にとらわれません。幅広い音の世界を自由に使って、音色の豊かさを表現しているのです。
さらに他の管楽器が加わってきても、音楽は比較的透明な質感を保っています。複数の主題的な旋律が重ね合わされていても、それぞれの音の流れを個別に追うことができます。そして低音域の弦楽器が、音楽全体の土台となる脈打つような基盤を提供します。この序奏部分は、最初のファゴット独奏が再び現れることで締めくくられます。
原始的な力強さ
続く「思春期の踊り」の部分では、音楽の性格が一変します。生々しい打楽器的な和音が、原始的なビートで聞き手を圧倒します。この和音の複合体は何度も繰り返されますが、その構造は非常に複雑で、多くの音が層のように重ね合わされています。しかもこれらの音は不協和音を形成しているため、その打楽器的な力がさらに強烈になっています。
その結果生まれるのは、原始的に打ち鳴らされる音の巨大な建造物のような響きです。聞く人の体は、この強烈な音響に共鳴せずにはいられません。
20世紀音楽の特徴
著者は、ここまでの「春の祭典」の分析だけで、20世紀音楽を特徴づける多くの根本的な要素がすでに現れていると指摘します。
まず旋律について。20世紀の音楽では、旋律は騒々しいほど自由に流れます。対称性や反復、抒情性といった従来の音楽に期待される要素に縛られることがありません。
和音についても同様です。複数の音楽的調を同時に使用する「多調性」5という手法によって、複雑な不協和音が生み出されます。これまでにない強烈でスリリングな響きが実現されているのです。
リズムも、従来の厳格な拍子の枠から解放されることで、非常に興奮的で生命力にあふれたものになっています。
こうした音楽を理解し楽しむためには、聞く側にも新しい姿勢が必要です。能動的で目覚めた、新鮮な聴き方6をしなければなりません。慣れ親しんだ従来の音楽に対する期待を持ち込んでしまうと、まるで温かいお湯に身を沈めるように受動的になってしまい、この音楽の真価を理解することができないのです。
時代とともに変わる受容
「春の祭典」に対する評価や理解は、その意図を把握することと深く関わっています。今日私たちがこの作品を聞く時、1913年の初演時7に聴衆の間でほぼ暴動が起きたということを想像するのは困難です。ちなみにこれは、画家カンディンスキー8が抽象絵画「コンポジション第13番」9を描いた同じ年のことです。
実際、パリでの初演を指揮したピエール・モントゥー10は後に、聴衆が投げつけるトマトから演奏者とダンサーを守るために、金管楽器の大きな和音で演奏を途中で打ち切らなければならなかったと証言しています。
しかし初演からほぼ1世紀が経った現在、聞き手は「春の祭典」の活力的で推進力のある、多リズム11で多調性の特徴を容易に理解し、受け入れることができます。この音楽は現代の私たちにとって活気に満ちたものであり、現代生活のリズムと全く矛盾しない自然なものとして感じられます。つまり私たちは今、真の意味でストラヴィンスキーの音楽を聴くことができるようになったのです。
脚注
1 「春の祭典」(Le Sacre du printemps) – 1913年に初演されたストラヴィンスキーの代表作の一つです。もともとはセルゲイ・ディアギレフ率いるバレエ・リュス(ロシア・バレエ団)のために作曲されたバレエ音楽でした。「古代ロシアの春の祭りにおける人身御供の儀式」をテーマとしており、原始的で野性的な力強さが特徴的な作品です。従来の調性音楽の枠組みを大胆に破り、20世紀音楽の出発点となった記念すべき作品として音楽史上重要な位置を占めています。 ↑
2 ファゴット(bassoon) – 木管楽器の一種で、通常はオーケストラの低音域を担当します。2枚のリードを用いるダブルリード楽器で、長い管を二つ折りにした独特の形をしています。一般的には深みのある低音で知られていますが、高音域では非常に独特で幻想的な音色を生み出します。「春の祭典」の冒頭では、この楽器の最高音域付近が使用されており、まるで別の楽器のような神秘的な響きを創り出しています。 ↑
3 拍子・メーター – 音楽の時間的な区切りを示す概念です。通常の音楽では4拍子(強・弱・中強・弱)や3拍子(強・弱・弱)など、一定のパターンが反復されることで、聞き手は予測可能なリズムの流れを感じることができます。しかし「春の祭典」では、このような規則的な拍子が絶えず変化するため、従来の音楽に慣れ親しんだ聞き手は戸惑いを感じることになります。この手法は後に「変拍子」と呼ばれ、20世紀音楽の重要な特徴の一つとなりました。 ↑
4 不協和音 – 音楽理論において、緊張感を生み出し、解決を求める響きのことです。従来の調性音楽では、不協和音は協和音(安定した響き)へと解決されることが期待されていましたが、20世紀の音楽では不協和音それ自体が表現の目的となりました。ストラヴィンスキーは不協和音を意図的に多用することで、原始的で野性的な力強さを表現し、聞き手に強烈な印象を与えることに成功しています。 ↑
5 多調性(ポリトナリティ) – 複数の異なる調性を同時に使用する20世紀音楽の技法です。従来の音楽では一つの楽曲は基本的に一つの調(ハ長調、イ短調など)に基づいて作曲されていましたが、多調性では例えばハ長調とヘ♯長調を同時に響かせるといったことが行われます。これにより、従来では考えられないような複雑で刺激的な響きが生まれます。ストラヴィンスキーはこの技法の先駆者の一人であり、「春の祭典」でその効果を存分に発揮しています。 ↑
6 能動的で目覚めた、新鮮な聴き方 – これは人智学的な芸術観の核心的な概念の一つです。ルドルフ・シュタイナーの人智学では、芸術作品との関わりにおいて受け手の積極的な参与が重要視されます。従来の音楽のように予定調和的な展開に身を委ねるのではなく、常に注意深く、創造的に音楽に向き合うことが求められるのです。これは単なる美的体験を超えて、人間の意識の発達と深く関わる問題として捉えられています。 ↑
7 1913年の初演 – 1913年5月29日、パリのシャンゼリゼ劇場で行われた「春の祭典」の世界初演は、音楽史上最も有名な「スキャンダル」の一つとして知られています。バレエ・リュスによる上演でしたが、革新的すぎる音楽とニジンスキーの振付に観客は激しく反発し、会場は大混乱に陥りました。賛成派と反対派が怒号を交わし、投げつけられた野菜や果物が舞台に飛び交ったと記録されています。この出来事は、芸術の革新がいかに社会に衝撃を与えるかを象徴する事件となりました。 ↑
8 ワシリー・カンディンスキー(1866-1944) – ロシア出身の画家で、抽象絵画の創始者の一人とされています。もともとは法学者でしたが、30歳で絵画の道に転じました。色彩と形の純粋な表現力を追求し、具体的な対象を描かない抽象絵画という全く新しい芸術領域を開拓しました。音楽と絵画の類似性について深く考察しており、しばしば自分の作品に音楽的なタイトルをつけていました。シュタイナーの人智学とも接点があり、精神的な芸術を目指していた点で、この論文の文脈と深く関わっています。 ↑
9 「コンポジション第13番」 – カンディンスキーが1913年に制作した抽象絵画作品です。「コンポジション」シリーズは、彼の最も重要な作品群の一つで、音楽の「コンポジション(作曲)」という言葉を絵画に応用したものです。具体的な対象を一切描かず、色彩と形のみによって精神的な内容を表現しようとした革新的な試みでした。ストラヴィンスキーの「春の祭典」と同じ1913年に制作されたことは、この時代が音楽と美術の両分野において同時に大きな変革期であったことを示しています。 ↑
10 ピエール・モントゥー(1875-1964) – フランス生まれの指揮者で、20世紀音楽の発展に大きく貢献しました。バレエ・リュスの指揮者として、「春の祭典」をはじめとする多くの革新的な作品の初演を手がけました。優れた技術と音楽的洞察力により、当時としては演奏困難とされた現代作品を次々と成功させ、新しい音楽の普及に努めました。後にアメリカでボストン交響楽団やサンフランシスコ交響楽団の音楽監督を務め、国際的に活躍した名指揮者です。 ↑
11 多リズム(ポリリズム) – 異なるリズムパターンを同時に組み合わせる音楽技法です。例えば、2拍子と3拍子を同時に演奏するといったことが行われます。これにより、複雑で躍動的なリズムが生まれ、聞き手に強い刺激を与えます。アフリカ音楽やジャズなどでは伝統的に用いられてきた技法ですが、クラシック音楽の分野では20世紀に入ってから本格的に取り入れられるようになりました。「春の祭典」はこの技法を効果的に使用した代表作の一つです。 ↑